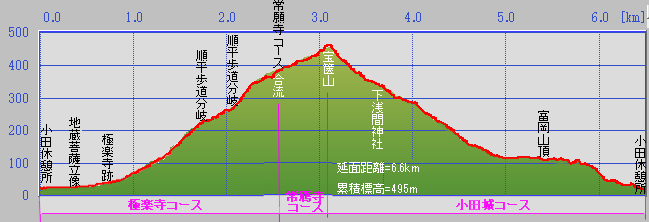https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7925905.html![]()
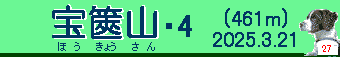
![]()
|
|
|
|
|
「3月中旬に関東地方に降雪」の異常天気の為か、低山でも花の便りが少ない中、 過去3回(下記)訪ねた茨城県の「宝篋山」で「コブシの花」が咲いていたとの記事を見つけ、3コースの中から最も短時間で登降可能コースを選び、金陽日の出発を決めた。 ◇所要時間:
3時間23分 <過去の「宝篋山」の記録> |
|
3時30分、出発。 首都高〜常磐自動車道を使って5時15分、「北土浦IC」を降りると残距離は9km。 国道125を西進して「小田十字路」を右折し、120m先の「←極楽寺」標識に従い左折して「宝篋山小田休憩所P」に到着すると先着車が3台。無風快晴ながら気温は2度。 5時33分、山頂に電波塔のある「宝篋山」を北に見ながら「常願寺・極楽コース→」標識に従い、東への農道へ出発。 |
|
|
|
|
|
|
|
冷気に霧が立ち込める景色を楽しみながら三分岐の「←常願寺コース」標識に従い、山を目指す。 |
道脇に鎌倉時代の「地蔵菩薩立像」。「湯地蔵」とも呼ばれ、安産と乳が出る祈願の地蔵として小田の人に守られてきたとのこと。 |
|
|
|
|
|
その先に「極楽寺公園」。寒さの中「水仙」、 |
赤い「ボケ」や |
|
|
|
|
|
純白の「こぶし」が花を見せた。Pから1kmほど先の森入口に「山頂まで2.3km」標識。 |
鶯の鳴き声を聞きながら、常緑樹の森を沢沿いに上っていく。 |
|
|
|
|
|
このコースには椿が多く、頭上やコースに紅色が華やか。 |
標高約230mの分岐標識に従い右折すると・・ |
|
|
|
|
|
6時27分、その先は南に視界が開けた裸地。標識の「順平歩道」で東の森へ進み、次の三分岐の「極楽寺コース・山頂まで1.1km→」指示に従い |
山頂を目指すとコース脇に春の山菜。「ぜんまい」と思って撮影したが・・帰宅後の調べでは「こごみ」らしい。 |
|
|
|
猪の掘り返し跡の多い山道で30mほど高度を上げると・・ 「こぶしの大木」。 まだ裸木状態だった。 更に20mほど高度を上げて・・ |
|
標高約350mまで上るとコース脇に「←こぶし道で山頂へ」標識。標準コースを外し、左斜面への山路へ進む。 |
|
|
|
|
|
標高約400mの未だ芽吹き前の桜の広場で正規コースへ合流し、小休止後、山頂を目指す。 |
|
山頂下30m辺りで「バイオ・トイレ」前を通過し、擬木階段〜車道で山頂を目指す。 |
|
|
|
|
|
7時23分、「宝篋山461m」山頂へ到着して「宝篋印塔」をバックに記録写真を残す。 |
「宝篋印塔」とは・・中国から伝来した仏塔の一種。日本で独自の発展を遂げ、墓碑塔や供養塔に使われる塔。 |
|
|
|
|
|
南には・・・その名の通り霞んだ「霞ヶ浦」、 |
西には「筑波山」。無風快晴・気温は約3度。 |
|
|
|
|
|
7時30分、「小田城コース」で下山を開始。このコースは見ものが少なく、唯々下る。 |
山頂から100mほど高度を下げると東に展望が得られる「下浅間神社」で大鳥居の割にお社は石の小社。南へ下りを続行。 |
|
|
|
|
|
標高290m辺りに「硯石」看板。解説板は無かったが、漢方の薬材などを粉にする薬研(やげん)の窪みが付けられていた。 |
標高108m地点に「要害展望所」。鎌倉時代には南麓の「小田城」の物見台があった地点かも??。 |
|
|
|
|
|
コースが南へ下り始める地点の西に好視界。先ほど通過した「要害展望台」が望めた。緩く東へ高度を下げていくと・・その先の「大師堂」先に沢山の |
地蔵菩薩石像。この先は簡易舗装路を下る。 8時56分、駐車場に戻ると駐車場は満車。帰路に就き、首都高の渋滞に巻き込まれ、往路の2倍の時間をかけ 12時50分、やっと帰宅。 |